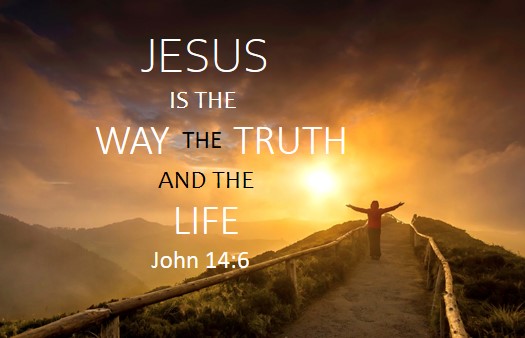ピラトとは私たちである
聖書箇所;ヨハネの福音書19:1~22/メッセージ題目;ピラトとは私たちである 「茨城世の光伝道協力会」、今週金曜日に総会がうちの教会の礼拝堂を会場に開かれますが、この協力会の機関紙の名前は「茨の城を花園に」といいます。茨城県がまだまだ福音宣教が大いになされるべき荒野のような場所、というイメージをかきたてられます。まさに茨城は「茨の城」、茨の地です。 茨、というものは、アダムの罪以来、土地がのろわれたゆえに地が生えさせたのろいの象徴です。そう考えますと、茨城とは、なんと重い名前だろうか、と思わざるを得ません。うちの教会の所在地なんてどうでしょうか? 茨城県東茨城郡茨城町、「茨」がこれでもかと出てきます。それだけに、冗談ではなく、茨の冠をかぶられたイエスさまをより深く思い、茨の地、茨城を覚えてとりなして祈る私たちとなりたいと、切に思います。 さきほどお読みしたみことばの中に、茨の冠をかぶせられたイエスさまのお姿が登場します。この冠をかぶせたのは、総督ピラトです。 私たちが礼拝ごとに告白する「信徒信条」の中に、「ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け」というくだりがあります。この告白には、ローマ総督として実在したポンテオ・ピラトの下でイエスさまは確実な苦しみを受けられた、ということ、また、ポンテオ・ピラトとはイエスさまを苦しめた張本人であった、ということが明らかにされています。 しかし、私たちがいつも礼拝のたびに、ポンテオ・ピラトの名前を口にして、ああ、彼は悪い人だ、という理解にとどまっているだけならば、私たちの信仰はまだ幼い段階にあります。私たちにもし、自分こそがイエスさまを十字架につけた罪人だ、という意識があるならば、この「ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け」という告白には、心が痛むのではないでしょうか? ああ、ポンテオ・ピラトとは私のことだ。 今日はポンテオ・ピラトの姿から学びましょう。もちろん、反面教師としてのピラトですが、この姿は私たちの姿でもあります。私たちがイエスさまとの正しい関係を保つため、悔い改めるべき罪を悔い改めるため、ピラトの姿から学びたいと思います。 第一にピラトは、残忍な者でした。 ピラトは、イエスさまには十字架刑に当たる罪がないことを知っていました。ユダヤの宗教指導者たちは、自分たちの権威が失われるから、イエスさまをなき者にしよう……十字架につけて神にのろわれた者としてしまい、イエスさまの権威を一切葬り去ろう ……このようなユダヤの宗教指導者の言い分をそのまま認めるということは、ローマの権威を託された政治家の沽券にかかわることでした。 しかし、ピラトはここで自分に与えられた権威を、あらぬ方向に用いました。イエスさまを痛めつけたのでした。 みなさま、むちで打つといいますと、どんなイメージを受けますでしょうか? むかしの欧米などでの子どもの躾でしょうか? しかし、イエスさまに当てられたむちは、あんな細いものではありません。もっと太くて堅牢なものです。 東京の寄席に、落語の合間に手品を披露する、伊藤夢葉(いとうむよう)という手品師がいます。この人は舞台に登場すると、自己紹介のあいさつ代わりに、ブル・ホイップという、かなり長くて太いむちを取り出して、それを一振りします。バン! という、凄まじい音が客席に響きます。新宿末廣亭(しんじゅくすえひろてい)のような建物がめちゃくちゃ古い寄席でそれをやると、舞台が壊れるんじゃないかとひやひやしますが、夢葉さんによると、この大きな音は空気を切る音で、床には一切当たっていないとのことです。 ……でも、それだけの芸で、手品でもなんでもない、観客は拍子抜けして笑いだす仕掛けなのですが、私などはそれを見て、なんか勉強になったような気がしたものでした。ブル・ホイップ……イエスさまやパウロもあのようなむちでたたかれたのかな……あんなのでたたかれたらひとたまりもありません。 しかも、イエスさまの当時のむち打ち刑といえば、そのようなブル・ホイップのようなむちに、あちこち、石や鉄の破片を埋め込んでおき、それでたたくわけです。からだがずたずたに……すみません、前の席にはそういう話が大嫌いなお嬢さんが座っているので、詳しくは話しませんが、これで何度も叩かれたら、血まみれ、こぶだらけ、骨折、脱臼……。 それに飽き足らず兵士たちは、茨の冠をかぶせました。私たちがよく見かけるバラのとげのようなものではありません。もっとずっと太く、鋭いものです。これで頭を締めつけるなら、顔も血まみれになりますし、痛いでは済まないことです。 そして、「ユダヤ人の王さま、万歳」と嘲りながら、顔をたたきました。畏れ多くも神の子に対して、なんという侮辱でしょうか。ピラトたちはイエスさまのことを、肉体的に痛めつけるに飽き足らず、精神的に痛めつけることに快楽を見出していた、ということです。 注解書を読むと、このようにイエスさまを痛めつけた上でユダヤ人の前に引き出したのは、この哀れな姿を見るがいい、この姿に免じて、おまえたちの言うところの「罪」を許してやれ、と、ピラトがユダヤ人たちにあわれみを乞うたからだ、と説明するものもあります。 たしかに、そのような要素はあったでしょう。しかし、そうまでしてユダヤ人のあわれみに訴えようとしたのならば、なぜこのむち打ちをユダヤ人の面前でではなく、総督官邸の中という、ユダヤ人の見ていないところで行なったのでしょうか。百歩譲って、激しいむちうちのあとが残る形でイエスさまをユダヤ人の前に出したとしても、そのような形が残るわけでもないあざけり、ユダヤ人の王さまがどうたらこうたら、とか、証拠も残らないことを兵士たちがすることを、なぜピラトは許したのでしょうか。 それは、それだけ残忍だったからとしか説明のしようがありません。さすがはピラト、ガリラヤ人を虐殺し、彼らが神さまにささげるいけにえに彼らの血を混ぜるようなことをしただけのことはあります。 しかし、ピラトだけが特別な罪人なのでしょうか? 私たちはどうなのでしょうか? 詩篇1篇1節にはこのようにあります。幸いなことよ、悪しき者のはかりごとに歩まず、罪人の道に立たず、嘲る者の座に着かない人……このことばから詩篇が始まっているのは象徴的です。それは私たち人間がみな罪人であり、悪しき者にふさわしいはかりごとをする者であり、人を嘲る者だからである、ということではないでしょうか? それなら私たちは、みなピラトのようであり、詩篇1篇1節の語る「幸いな人」の反対に当たる人ということではないでしょうか? そう考えると、私たちは残忍なのです。いや、私はそんな残忍ではありません、それが証拠に、イエスさまのことを迫害していません、私はピラトとちがいます、と言いますでしょうか? しかしほんとうのところ、私たちは人をのろい、神をのろうような罪人です。行動に移さないだけで、私たちは残忍なのです。 ヤコブの手紙によれば、人をのろうということは、神にかたどって造られた存在をのろうということです。それはとどのつまり、神をのろうということ、神の子イエスさまを迫害することにならないでしょうか? 私たちは正義の味方になったつもりで人をさばきますが、問題なのは人を憎むこと、人を見下げることそのものです。 それは実のところ畏れ多いこと、神をも恐れぬことをしていることを、私たちはもっと意識する必要があります。繰り返します。私たちは残忍なのです。 私たちがだれかのことをあざけったり、こきおろしたりすることなら、それはイエスさまに対し、むちをふるうことです。神さまがご自身のかたちに創造された存在をのろうことを私たちがしているかぎり、私たちはその責めを負うことになります。私たちがこの責めからのがしていただくためには、まず私たちはそのような罪人、神の子にむちを振るう罪人であることを認める必要があります。このことを認めることはとてもつらく、直視に耐えないことですが、するしかありません。そこから私たちは、血まみれの罪からのがしていただく道が開けます。 第二にポイントにまいります。ピラトは、保身の者でした。 ピラトは、血まみれになり、さらにはあわれな王の格好をさせられたイエスさまを宗教指導者たちの前に連れてきました。どうだ、見たか、これで気が済んだだろう……しかし、ピラトの目論見は失敗に終わりました。彼らはこんなになったイエスさまを見てもなお、十字架につけろ、十字架につけろ、と叫びつづけました。 この叫びに対し、ピラトは言います。おまえたちがこの人を引き取り、十字架につけるがよい。私はこの人に罪を見出せない。 要するにピラトは、イエスさまを十字架につける責任者という立場から逃げようとしたのです。責任者はおまえたちだ。私は知らない。ピラトの保身が読み取れます。 しかし、ユダヤ人たちは容赦しませんでした。私たちには律法があります。その律法によれば、この人は死に当たります。自分を神の子としたのですから。 律法は何と言っていますでしょうか? 彼ら宗教指導者たちは、レビ記24章16節を適用した模様です。神の御名を汚した者は死刑に処せられる。ご自身を神の子であると告白したイエスさまは、宗教指導者たちにしてみれば、神の御名を汚した者ということになります。 だが、彼らにとって律法がそれほど大事なものの割に、彼らはきわめて重要なことを、意図して捻じ曲げています。まず、ご自身が神の子であるとイエスさまが告白されたことを神への冒瀆と判断したことは、ユダヤの宗教指導者という人間しての判断でこそあれ、神さまご自身によるご判断ではありませんでした。彼ら宗教指導者たちがねたみゆえにそのような判断を下したとわかる余地があり、ピラトもそのことに気づいていました。 また、よしんばそれが神への冒瀆だったとしても、彼らにとってそれほど神さまとそのみことばが大事な割には、処刑の方法が間違っていました。 神への冒瀆をした者は石打ちで処刑されるべきでした。ステパノの殉教もそのようにして石打ちで殺されたものでした。それが十字架だというのです。石打ちで死ねば英雄の殉教と見なされるでしょうが、十字架で死んでは何をどうしても、のろわれた極悪人にしかなりません。ユダヤ人がイエスさまに手を下すには、十字架以外に方法がなかったのでした。 しかし彼らユダヤ人は、勝手に人を十字架で処刑することなど許されていませんでした。もしそれをしてしまったら、それは宗主国ローマに対する越権行為であり、十字架刑を施したほうが重罪に問われます。したがってユダヤ人がイエスさまを十字架につけるには、ローマの権威を用いるしかなく、ローマの全権を帯びた総督ピラトを動かすしかなかったのでした。 しかし、当のピラトにしてみれば、せいぜいそれはユダヤ民族の内輪のもめごとに過ぎません。いかにピラトが残忍でも、無実の者をよりにもよって十字架刑に処するわけにはいきません。 だがここで宗教指導者たちは、イエスはわれらの律法によれば死刑だ、とピラトに迫りました。その一方ですでにユダヤ人たちは、私たちはだれも死刑にすることが許されていません、とも言っています。つまり、私たちユダヤ人が死刑と決めた者は、ピラトよ、あなたが死刑にしなければならないのです、ということです。 ピラトは震え上がりました。今度はピラトは、あらためてイエスさまに尋問することにしました。あなたはどこから来たのか、と問いますが、その問いに黙秘を貫かれるイエスさまに対し、ピラトは、私に話さないのか、私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを、知らないのか、と迫りました。 だが、ピラトはここで重大な勘違いをしていました。ピラトには実際のところ、イエスさまを釈放する権威も十字架につける権威もありませんでした。 ピラトのその権威は、ローマ帝国という後ろ盾があってはじめて存在するものでした。いえ、もっと言えば、そのローマ帝国の権威すら、全地の王であられる神さまの権威があって初めて成り立っているものでした。 イエスさまはそんなピラトの尊大な勘違いを指摘され、おっしゃいました。上から与えられていなければ、あなたはわたしに対して何の権威もありません。ですから、わたしをあなたに引き渡した者に、もっと大きな罪があるのです。 ピラトとちがって、イエスさまをローマの権威に引き渡したカヤパたち宗教指導者は、そもそも権威とは何かということをよくわかっていましたし、またわかっていなければならない立場にありました。彼らにとっての権威は、神さましかないはずです。だが彼らは、神さまよりもピラトの権威を上だと見なし、畏れ多くもそのこの世の権威にイエスさまを引き渡すということをしたのでした。 ピラトも残忍、また尊大、それでいて卑怯という点において大いなる罪人でしたが、イエスさまはそれ以上にカヤパたちの罪が大きいとおっしゃいました。その姿は、ついには「カエサルのほかに、私たちに王はありません」と告白した姿に明白に現れました。かつて彼ら宗教指導者たちは、カエサルに税金を納めることは律法にかなっていますか、かなっていませんか、とイエスさまに迫りました。あのことばとなんとも矛盾していますが、イエスさまをなき者にしようという点で、宗教指導者たちのことばは一致していたと言えます。 だからといって、ピラトの罪が減じられるかというと、そんなことはありません。やはり使徒信条が告白するとおり、「ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け」なのです。いかなる理由であれ、ピラトが判断を下したからこそ、イエスさまは十字架につけられたのです。 暴動が起こったらその責任を問われ、ローマ総督の座を追われるかもしれない……マタイの福音書によれば、ピラトは水を持ってこさせてそれで手を洗ってみせ、自分の責任を逃れるパフォーマンスをしました。 だがやはり、ピラトは残忍な男でした。ヨハネの福音書には書いてありませんが、ほかの福音書を読むと、ピラトは判決を下してイエスさまのことを十字架につけるにあたり、ただでさえむち打ちで血まみれ、傷だらけになっていた主のみからだを、まるでだめ押しのようにむち打ちにしました。自分には責任がないなんて大嘘です。責任は大ありなのです。 エデンの園で、善悪の知識の木の実を食べたことを神さまにとがめられたとき、アダムは言いました。「あなたが私のそばに置いた女が食べろと言ったので、私は食べたのです。」エバは言いました。「蛇が私をだましたのです。」人の罪とは、自分が罪を犯したことを、神さまのせい、他人のせい、悪魔のせいにして、けっして自分で責任を取らないことです。しかしはっきりしていることは、何をどうあがこうとも、その罪の責任は必ず自分が取らなければならないことです。 保身に走って罪の責任から逃れようとするピラトの姿は、私たちの姿です。自分が罪を犯したことを神と人の前に認めることは、とても難しいことです。 しかし、しなければならないことです。だからこそ私たちは、神さまのあわれみにすがる必要があります。イエスさまは、罪を認めて悔い改めることも簡単にはしないような、そんな私たちであることをご存じで、そんな私たちの身代わりに十字架にかかってくださいました。私たちは、自分の中には罪を認めて悔い改める力はありません。日々十字架の前に自分を引き出し、ひざまずくのみです。 第三のポイントにまいります。ピラトは、はからずも主のみこころを成し遂げた者でした。 ピラトは言ってみれば、負けたのでした。それも、自分が支配しているはずのユダヤの宗教指導者たちに負けたとは、たいへんな屈辱というべきことでした。ピラトはイエスさまの十字架に掲げる罪状書きに「ユダヤ人の王、ナザレ人イエス」と書きました。それも、ヘブル語、ラテン語、ギリシア語なので、エルサレムに過越の巡礼に来ていた人は、みんなそれを読んで理解できる仕掛けになっていました。 もちろん、宗教指導者たちはピラトのこの措置に不満をいだきました。われわれが十字架につけたのはユダヤ人の王ではない、ユダヤ人の王を自称した者だ。 しかし、ピラトはここで最後の抵抗をしました。「私が書いたものは、書いたままにしておけ。」これはもともとのことばを直訳すると、「私が書いたものは、私が書いたのだ」となります。これは要するにこういうことです。ユダヤ人どもよ、おまえたちがイエスを十字架につけたのは、私ピラトの権威によってではないか、ならば、イエスを十字架につけるだけの罪状を定める権威は私ピラトにあると認めよ、おまえたちユダヤ人は、この件について一切発言することを許さぬ……。 もし罪状書きに、ユダヤ人の王を自称したと書いたならば、それこそピラトはユダヤ人の言い分に屈服したという証拠になり、ピラトの面目は丸つぶれです。ではなぜ、ピラトは罪状書きを「ユダヤ人の王」にしたのでしょうか? それは、ピラトがイエスさまを尋問してきた中で、「ユダヤ人の王」ほどふさわしい「罪状書き」はなかったと確信したからではないでしょうか? とは言いましても、なぜ、ピラトがその確信に至ったかは、ピラトの心理分析のようなことを行なっても、恐らく正解は出てきません。確実に言えることは、ピラトはイエスさまのみことばを聞いて、イエスさまのおっしゃっている「ユダヤ」とは、自分が支配している「ユダヤ」のこと、という意味以上に、イエスさまのみことばをお聴きしてお従いするすべての人のこと、という、それまで考えてもみなかった真理を教えられたことです。…