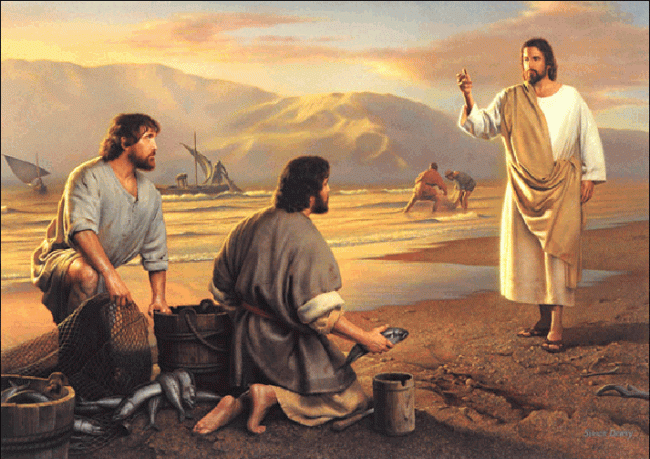「イエスさまの『追っかけ』は報われる」
聖書朗読;マルコの福音書6:53~56/メッセージ題目;「イエスさまの『追っかけ』は報われる」/讃美;聖歌617「したいまつる主の」/献金;聖歌569「主よこの身いままたくし」/頌栄;讃美歌541/祝福の祈り;「主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、私たちすべてとともにありますように。アーメン。」 今は何というのか知らないが、歌手であれ俳優であれ、特定のスターのファンが昂じると「追っかけ」となる。谷村新司の歌に「スーパースター」という、「追っかけ」の若い女性の気持ちを歌った曲があるが、その出だしはこうである。「テレビからほほえみかける 貴方を追いかけて街から街へ 誰よりも近くにいたい そんな毎日だったわ」だれよりもそのスターの近くにいたい毎日、それが追っかけで、この歌は、雨の日も暗くなるまで事務所の外で立ちつくしてた、誰よりも早く知ったわ、貴方のスケジュール表……という歌詞につづく。 結局、この歌の主人公の女性は、母親を支えなければと決意して、会社に就職して「追っかけ」であることをやめる。なんとも切ない歌だが、それなら「イエスさまの追っかけ」ならどうだろうか? 悲しい結末を迎えるだろうか? 今日の本文にいこう。これは「イエスさまの追っかけ」の記録である。今日の箇所は1節ずつ、3つの面から「イエスさまの追っかけ」たる群衆の姿、信仰の表れを見ることができる。それではともに見ていこう。 ①イエスさまに気づく信仰 「彼らが舟から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついた。」(54節) 彼らがすぐに、そこに来た人がイエスさまだと気づいたのは、普段から彼らの関心がイエスさまに向かっていたから。ラッキーFMが聴きたい! となっていたら、なにがなんでも、チューニングをFMの94.6MHzに合わせておくだろう。チューニングが合っていたら、あとは受信すれば聴きたい番組が聴ける。そのように、関心がイエスさまにつねに向かっているからこそ、いざイエスさまが現れたら、それとわかるのである。 彼ら群衆には、イエスさまのみことば、イエスさまのみわざへの飢え渇きがあった。それ以上に、イエスさまのご存在に対する飢え渇きがあった。イエスさまでなければその飢え渇きを満たすことはできないことを、彼らのたましいはよく知っていた。彼らはパリサイ人のような宗教指導者のところに行かなかった。イエスさまのもとに行った。 私たちがこうして、礼拝をおささげするのも、毎日聖書を読んでお祈りするのも、私たちには、イエスさまでなければ満たせない飢え渇きがあるからである。しかし、この世は情報の洪水で、いろいろなものが私たちに、魅力的な姿をして近づいてくる。しかし、そのようなものによっては、私たちのほんとうの飢え渇きを満たすことはできない。それはどんなに素晴らしくても、この世に属するものでしかない。 もし私たちが、いつでもイエスさまのご存在とみことばに飢え渇いているならば、私たちはすぐにでも満たしていただける。私たちはみことばを読みたくてたまらなくなるし、そうして手を伸ばしたみことばによって、たましいが潤され、生きる、という体験をする。 私たちはイエスさまによって飢え渇きが満たされることに期待しているだろうか? そうでなければ私たちは世のもので満たそうとし、それではけっして飢え渇きは満たせない。渇いているならわたしのもとに来なさい、このイエスさまの呼びかけに、いまお応えしよう。 ②イエスさまへと走り回る信仰「そしてその地方の中を走り回り、どこでもイエスがおられると聞いた場所へ、病人を床に載せて運び始めた。」(55節) 「追っかけ」たるゆえんである。しかし、これは単なる「追っかけ」ではない。彼ら群衆は、イエスさまでなければ自分たちのいのちを生かすことができないことを知っていた。霊がいのちを得るために、彼らは必死だった。 彼らは、イエスさまがそこにいるという情報に敏感だった。いや、そればかりではない。イエスさまが来られたと知るや、とにかくそこに駆けつけることを最優先にした。病人を床に載せたという難儀な状態でもかまわず、イエスさまのもとに駆けつけることに必死だった。 こんにち、キリスト教会に足りないのは、この、イエスさまの御顔を求める熱心さではないだろうか。礼拝堂がそこに建っていて、牧師がいつでもそこにいる、手許にはいつも聖書がある、YouTubeにつなげばいつでも好きなだけメッセージが聴ける……。 みなが飢えているなら、白いお米のご飯もごちそうになる。しかし、飽食の時代に、ご飯はありがたいものと思えなくなる。神さまの恵みが無視されている。やがて食糧難が訪れることが警告されていても、みな知らん顔である。 聖書は、食べ物の飢饉ならぬ、みことばに対する飢饉の時代が来ることを警告している(アモス8:11)。それは、聖書が禁書になるような時代が来ることを、私たちクリスチャンが許すからかもしれない(実際、韓国ではかつて、聖書を18歳未満に読ませないようにする運動が起こったことがある)。しかし、もっと根本的なことを言えば、私たちクリスチャンがこの世の快楽にうつつを抜かし、聖書なんていらない、となるからではないだろうか。そうなったら、神さまは、そんなにおまえたちがわたしのことばを必要ないというなら、やらない、とおっしゃらないだろうか。 自分が救われたい、愛する人に救われてほしい、と願うなら、千里の道も遠くなかった。私たちに求められているのは、この行動である。 神さまはもちろん、私たちとともにおられる。しかし、私たちの側から積極的に近づくということを、果たして私たちはしているだろうか? 今日こうして私たちが礼拝の場に集っているのは、霊の飢え渇きを主にあって満たす行動である。集えたことに感謝しよう。そして、自分も、ほかの人も、とても救いを必要としているという現実を、さらにしっかりと認識し、それに見合った行動をしよう。礼拝しよう。祈ろう。みことばを読もう。交わろう。伝道しよう。 ③イエスさまに触れる信仰「村でも町でも里でも、イエスが入って行かれると、人々は病人たちを広場に寝かせ、せめて、衣の房にでもさわらせてやってくださいと懇願した。そして、さわった人たちはみな癒やされた。」(56節) 彼らはイエスさまに近づいただけではない。さわったのである。 本日は大相撲九州場所の千秋楽。いまはコロナ下だからしないが、大相撲で勝って取組を終えたお相撲さんの体を、観客が花道に向かって手を伸ばし、ペタペタ触るのをご覧になったことがあるだろう。あれは「勝利にあやかりたい」という、相撲ファンならではの信仰にも似たものだと思う。アイドル歌手の握手会の人気もそのたぐいのものだろう。 イエスさまにさわるのは、イエスさまにあやかる、ということ。さわったらその瞬間、相手と一体化する。イエスさまを前にして、平静を装うのは、一体化したいところまでイエスさまのことを求めていない、ということではないか? 思うに、日本のクリスチャンはみんな静かすぎる。イエスさまに触れることにガツガツしていない。 それが日本人の国民性だ、美徳だ、とおっしゃるかもしれないが、お酒を飲んだり、お祭りになったりしたら大はしゃぎするという面も、日本人は持ち合わせているではないか。放蕩に酔うことをするのに、なぜ御霊に満たされ、御霊に酔うことをしないのか? 御霊とは人を「酔わせる」お方である。 酔うと狂うが、狂うことを恐れてはならない。なぜなら、正しく狂えば、人に対しては正気になるからだ(Ⅱコリント5:13)。また、人が主に狂うことをむやみに批判するのもよくない。その人は主との関係で狂っているのである。ダビデを見よ。王さまであろうとも構わず狂ったが、その狂う姿ゆえに、へりくだった者はかえって尊敬した(Ⅱサムエル6:21〜22)。 私たちも狂ったようにイエスさまに近づき、恥も外聞もなくベタベタさわることを恐れてはならない。あの人、あんなにのめり込んでいる、という人もいようが、私たちは悪いことをしているわけではない。むしろ、それで笑われるならば名誉ではないか。 イエスさまの追っかけ、イエスさまに狂って触る人は、癒される、という、最高の報いをいただく。私たちはみな、罪に病んだ存在である。そんな私たちも、イエスさま、十字架にかかられて復活してくださったお方に触れるならば、いやしていただける。罪の病を深刻に受け止めるならば、癒されたいと死に物狂いになり、とにかくイエスさまにすがるはずではないか。そこまで一生懸命になれるのは、イエスさまに触れれば癒されるという信仰があるからである。 私たちはイエスさまに触れれば癒やされる、という信仰を持っているだろう。その信仰を働かせていこう。折あるごとに呼び掛け、応えていただく、そのみわざを体験しよう。 そして私たちは、イエスさまにはどのように触るのかを人々に示そう。キリスト教とはひとことで言って、神との交わりである。この交わりを自分も体験するだけでなく、ひとも体験できるようにお仕えしていこう。