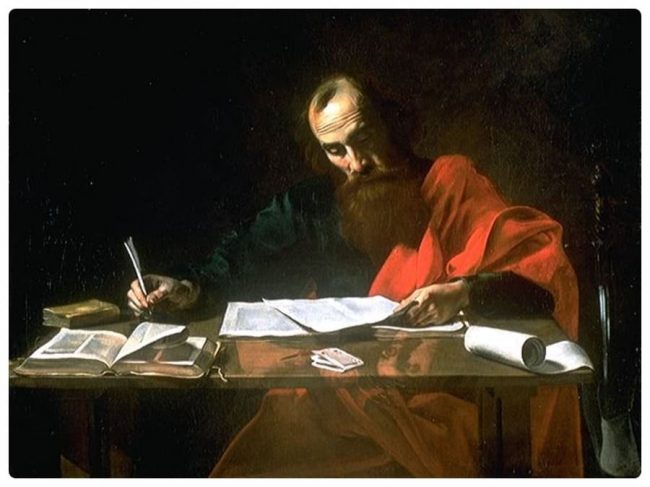「私たち聖徒は神の建物」
聖書箇所;コリント人への手紙第一3:9~17/メッセージ題目;「私たち聖徒は神の建物」 先週のメッセージの聖書箇所は、9節で締めくくっています。そのときの解き明かしで、終わりのことば「あなたがたは……神の建物です」ということについては、今週のメッセージで詳しく扱うことをお話ししました。そこでお約束したとおり、今日は、「あなたがたは……神の建物です」という、パウロのことばから学びます。 私がみなさまからお伺いして知っていることですが、うちの教会は長年、自前の礼拝堂を手に入れるために、聖徒のみなさまで一生懸命祈り、また、献金してこられました。基本的に外部の業者に頼まず、自分たちで一生懸命に建てられました。そうして建ったのがこの礼拝堂ですから、この礼拝堂が献堂されたときのみなさまの喜びはどれほどのものだっただろうかと思います。 教会というと私たちは真っ先に、礼拝堂をイメージするかもしれません。もちろん、聖書における「教会」というものは、そのような「建物」というよりはむしろ「人の集まり」「会衆」と解釈すべきです。それは今までも学んできたとおりです。しかし、「教会」を「建物」というイメージで受け取っても、あながちピントが外れていないかなと思えるのは、もしかしたら、今日学ぶ箇所のイメージが私たちクリスチャンにあるためかもしれません。 しかし、コリント教会に特定の礼拝堂がなくても、この群れをパウロが建物になぞらえたのは、やはり「神の建物」とは、目に見えて手でさわれる礼拝堂、チャペル以上に、主によって贖われた聖徒たちの群れを意味するということが前提になります。コリント教会が聖なる民、聖徒たちであるのと同様に、私たちも聖徒です。ゆえに、私たちも神の建物ということになります。 今日の聖書箇所はあらためて9節からを本文にして、17節まで、建物ということを扱った本文から、私たちはともに学びたいと思います。それではいつものように、3つのポイントからお話しいたします。 ①第一のポイントです。神の建物の土台はイエス・キリストです。 9節のみことばにあるとおり、神の目から見て私たち聖徒は、神の建物です。それでは私たちは、どのような建物なのでしょうか? まず、土台からして独特です。10節と11節のみことばをお読みします。 10節でパウロは、自分のことを建築家になぞらえています。ここでいう建築家は、家を建てる働きそのものをする「大工」ではなく、建てる作業の図面を描く「設計士」また、作業全体を見張る「監督」ともいうべき、大局から教会形成に関わる人です。どのようにすればこのコリントという都市に立てるにふさわしい教会がつくれるかを考え、それにふさわしく土台を据えるのです。 現実のコリント教会を見てみると、争いがあったり、派閥に分かれた分裂があったりと、目を覆わんばかりの醜態をさらしていて、それは主の教会としてとても証しにならないような状態にありました。しかし、忘れてはならないことがあります。そのような醜い有様をさらしていても、そのような者たちをイエスさまは十字架の血潮によって救い、あがなってくださったということです。彼らはどんなに醜くても、イエス・キリストを土台とした「神の建物」であることに変わりはありません。神さまのものです。救われているのです。 「あんなことをするような人が救われているのか?」などと思える言動をするクリスチャンというのはいるものです。しかし、これは間違えてはなりません。イエスさまを信じているかぎり、その人は救われています。ただ、イエスさまという土台にしっかり立て上げられるために、まだまだそのプロセスの中にある「工事中」の段階なだけです。工事中ならば騒音もします。セメントや溶剤のかぎたくないにおいもします。ほこりも立ちます。しかし、それらのことは、しっかり立て上げられるために必要なプロセスと考えれば、受け入れられるのではないでしょうか? 少なくとも「こんな人は救われていない!」などと、さばくものではありません。 さて、土台の上に家を建てるといえば、イエスさまのおっしゃったおことばを思い出します。マタイの福音書7章、24節から27節のみことばです。 洪水のような事態というものは、つねに変転する人生にはつきものです。現に今こうしていても、コロナという事態が起きていて、この洪水のような事態にもう1年半以上も私たちは翻弄されっぱなしです。しかし、仮にコロナが起きていなかったとしても、この平和な日本にかぎっても、地震だの台風だの、どうしようもない自然災害は起きるものです。これは不可抗力の災害のケースですが、私たち個人個人の人生にも、そのような嵐のごとき事態というものはつねに起こり得るものです。 このようなときに問われるのが、私たちが何に土台を置いているかです。私たちの土台がイエスさまであるならば、その人は安全です。言ってみれば、土台が人生全体を支えてくれるようなものです。イエスさまが土台でないということは、みことばを聴かないか、あるいは、聴いてもそのみことばを守り行わないということであり、そのような人の人生はいざというときにめちゃめちゃになります。 イエスさまと関係のない教会形成や教会生活というものは、イエスさまと交わりのない生活であり、そのような生活が、砂の上に家を建てる生き方です。私たち教会がほんとうに、土台がイエス・キリストであるというならば、いついかなるときも、イエスさまとの交わりの中に、各自が、そして教会全体が、生きる必要があります。私たちはその生き方を目指していますでしょうか? 実践していますでしょうか? イエスさまを土台とする生き方、教会形成にともに取り組む祝福を、ともにいただいてまいりましょう。 ②第二のポイントにまいります。神の建物は火によって判別されます。 12節、13節のみことばです。 何で建てるか。このみことばを見ると、その材料が、金、銀、宝石、木、草、藁とあります。 言うまでもないことですが、金や銀や宝石は、小さなものでもとても高いものです。宝石店や貴金属店に行くと、あんな小さなものがなんであんなに高いのか、と思うでしょう。 いわんやこの金、銀、宝石が、家を建てるほど大きな塊だったら、それはどれほど高く、また重いことでしょうか。だいいち、それを建材にするために加工するのもひと苦労です。それで建物を建てるということは、想像を絶するほど大変なことです。 これに比べると、木や草や藁で建物を建てることなど、実に簡単です。材料は手に入れやすく、建材として加工しやすく、軽いのですぐに建ちます。しかし、このような建物には最大の弱点があります。火です。火事になったらひとたまりもありません。 みことばを読むと、どのように建物を建てたかは「その日」における火の審判が明らかにするとあります。その火の審判はどれほどのものでしょうか? ペテロの手紙第二3章10節をお読みください。 怖ろしいばかりの描写です。しかし、これは現実です。私たちは知らなければなりません。私たちの地上の歩みは、ことごとく、このように火によってさばかれる終わりに向かっているということをです。その火が来たら、この世界に存在するものはことごとく焼き滅ぼされます。 その火の審判は何を明らかにするのでしょうか? 私たちクリスチャンが、イエス・キリストを土台として、いかに人生をともに立て上げてきたかということです。そもそも、木や草や藁のような建材で建物を建てるということは、イエス・キリストを土台にした生き方にしては安易なことであり、土台さえしっかりしていればあとは何をしてもいい、何をしても許される、という発想の産物です。そんな生き方は終わりの日には、何も残してはくれません。 逆に、イエスさまという土台は何にも増して素晴らしいから、その土台にふさわしいだけの犠牲を払って建物を建てようという行動につながっていくならば、それは金や銀や宝石で建物を建てるということになぞらえられます。たいへんなことですが、終わりの日にすべてが火によって焼き払われても、地上にキリストのからだなる教会をしっかり立てた、神の国を拡大した、ということのゆえに、神さまは私たちに対し、「よくやった、よい忠実なしもべだ」という、最大級の賞賛を与えてくださいます。 しかし、もし、イエス・キリストを土台にしたわりには大したことをしなかったならば、それは木や草や藁で建物を建てるようなもので、火で焼き払われておしまいです。 とはいっても、その人は救われないわけではありません。15節のみことばをお読みします。 土台がイエス・キリストであるかぎり、イエスさまに根ざした信仰のゆえに、その人は火をかいくぐって、天国に入れていただけます。しかし、それ以上のものではありません。やはり価値のない建て方をしたならば、それは永遠につづく神の国に益する働きと見なしてはいただけないのです。 しかし、このようなことを言うと、クリスチャンの歩みとはしょせん業績主義なのか、とか、亡くなる直前にイエスさまを受け入れるような回心を体験した人はどうなるのか、その家族が感動したことはどうなるのか、というようなことが気になってはこないでしょうか? しかし問題は、過去私たちがどうだったか、ちゃんと業績を残していたか、それが査定されている、ということではありません。問題は過去ではなく、現在なのです。もし、自分たちが今まで、イエスさまを土台としているクリスチャンとして、その土台にふさわしくない人生を立て上げていたということを知ったならば、私たちのすることは、ああ、こんな人生しか歩んでいなかったから、終わりの日の炎に焼かれてしまう、と、恐れることではありません。 私たちが求めるべきは、14節に書かれているとおりの生き方です。 報い、それは、神さまのために天国をともに立て上げたことを、神さまに認めていただけるという報いです。「よくやった、よい忠実なしもべだ」、この御声をお聞きしたいでしょうか? 今からでも金、銀、宝石を求め、それを加工して建物を建てるがごとく、神の栄光のため、主の御国のために生きることです。チャンスはまだ残されています。そのチャンスのあるうちに、聖徒という神の建物をともに立て上げる働きに献身してまいりましょう。私たちの共同体はこの地上に天国をあらわす存在です。ヨハネの黙示録の21章に描かれた天国の描写、ちょっとだけ見ましょう、18節から21節です。 この天国の麗しさは、そっくりそのまま、天国を地上に実現する私たちのことです。これが私たちなのです。 パウロのことばの意味はこうではないでしょうか? 麗しい金や銀や宝石で建てられているのがあなたたち、コリント教会なのですよ、木や草や藁で建てるような、安易な生き方をどうかやめなさい。 私たちも、終わりの日に神さまの栄光のために何が残せるでしょうか? 生きるチャンスが与えられているかぎり、最高のものを神さまのためにささげ、残す生き方を全うする私たちとなりますように、天国の麗しさを実現する私たちとなりますように、主の御名によってお祈りいたします。 ③最後に、第三のポイントです。神の建物は神の宮です。 16節、17節をお読みします。 私たちは何だとこのみことばは語りますか? そうです、「神の宮」です。私たちがひとつとなって、ひとつの宮、ひとつの神殿を形づくるのです。 コリントにも、創造主なる神さまを祀るものではなかったにせよ、神殿はありました。また、やはりコリントにはユダヤ人がいましたので、エルサレムで神殿を見たことがあるという人も多かったでしょう。神殿のイメージはそれぞれにそれなりにあったはずです。しかし、ほんとうの神殿はあなたたちなのです、あなたたちは、イエス・キリストの父なる神ご自身が神殿とされた存在です。パウロははっきり語りました。 神殿は何があってもけがされてはなりません。ましてや、壊されてはなりません。もし、けがれや破壊を神殿に持ち込むような者がいたならば、その者は制裁されなければなりません。その制裁を下すのは、神さまご自身です。 そもそも、神さまにとって神の宮、神殿をは何を指すのでしょうか? それは、目に見える建物ではありません。 究極的にそれは何を指すのか、さきほどお読みしたヨハネの黙示録21章のみことばの続きを読むと、このようにあります。ヨハネの黙示録21章22節です。 神殿とは聖徒たちであるとともに、イエスさまご自身、神さまご自身です。まさしく私たち教会が、キリストのからだであるゆえんです。絶対に壊されてはならないし、けがされてもなりません。その神殿が聖徒たちであるということならば、神殿をけがし、壊すということは、どうすることでしょうか? そうです、主にあって保たれるべき交わりを乱すことです。教会の中に派閥をつくり、争いを起こすなど、言ってみれば、宮をけがし、壊すということです。私たちが罪を犯してはならないのは、私たちが聖なるキリストのからだの一部分だからです。まさしく、第一コリント6章15節のみことばが戒めるとおりです。 もちろん、それだけではありません。信仰の共同体というものは、それを形づくる私たち一人ひとりの歩みも関わってくるものであり、もし私たちが不従順、不品行の歩みをしているならば、その歩みは自分ひとりの中だけで完結するものではありません。教会という神の宮全体に関わってくるものです。もし、宮のどこかに壊れた場所や、きたない場所があったならば、それで宮全体のイメージががた落ちするもので、それと同じことです。私たちは宮とされているものにふさわしくあるべきです。 私たちが神の宮であるという自覚は、2つの次元で持つべきものです。まずは、私たち一人ひとりが神の宮であるということです。私たちは一人ひとりが、心の中にイエスさまを迎え入れ、イエスさまを宿している存在です。私たち一人ひとりの生活を通して、私たちに関わる全ての人が、私たち一人ひとりの心の中におられるイエスさまに触れ、イエスさまの御名をあがめるようにするのです。 また、私たち教会という共同体が神の宮です。私たちの交わりの真ん中に神さま、イエスさまをお迎えしているわけです。私たちは今こうして、礼拝という共同体においてともに神さまを礼拝しています。また、私たちは礼拝が終わると、それぞれの場所に散っていきますが、それでも私たちは、水戸第一聖書バプテスト教会に属する兄弟姉妹という立場で、ひとつの共同体、ひとつの主のからだ、神の宮をなす存在です。 私たちはどうでしょうか? 私たちの土台はイエスさまであることをつねに自覚し、この岩なるお方の上につねに建物を建てるがごとき生き方を志していますでしょうか? この生き方はひとりひとりがするものですし、また、ともにするものです。 また、私たちはこの、だれよりも素晴らしいお方という土台の上に建てるにふさわしい生き方を目指していますでしょうか? いいかげんに生きることなく、それぞれが、また、ともに、イエスさまという土台にふさわしい最高の生き方を目指してまいりましょう。 そして、私たちはイエスさまをお迎えした、神の宮です。私たちをとおして神さまが礼拝されるのです。ひとりひとりが、また、ともに、神さまを証しする生き方に献身してまいりましょう。 そのようにしてともにこの地において、私たち聖徒たちがふさわしい生き方をすることによって、やがて来る終わりの日に恥ずかしくなく御前に立つものとなりますように、主の御名によって祝福してお祈りいたします。