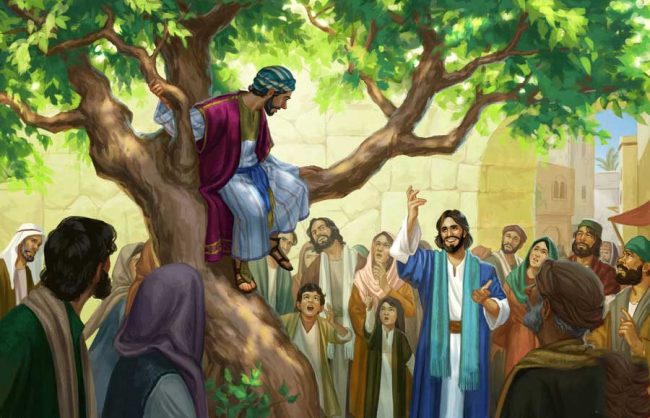「御前に完了する行い、愛」
a 聖書本文;ヨハネの黙示録3:1~6/メッセージ題目;「御前に完了する行い、愛」 前にもお話しした学生時代のことを、もういちどお話しします。ある日私は、学科の先輩と街を歩いていると、道端に占いをしている人がいました。先輩はそれを目ざとく見つけ、私に言いました。「武井くんも占ってもらいなよ。」しかし、占いなどとんでもないことです。私は言いました。「いえ、私はクリスチャンなので、占いはしないんです。」すると先輩は言いました。「えー、武井くん、『キリスト教』を信じてんのー?」 先輩の言っていることもわかりますが、私はそのことばに、少し違和感を覚えました。私はイエスさまを信じています。でも、「キリスト教」という「いち宗教」を信じているかのように言われたように思えて、心外でした。 のちに私はいろいろ見聞を深め、私たちの聖書信仰とその実践を「キリスト教」という客観的な呼び方をすることにやぶさかではなくなりました。が、それでも、私たちクリスチャンが「キリスト教」という宗教をやっているわけではない、という私の立場に変わりはありません。 問題なのは、クリスチャンがあたかもほかの宗教を信じるのと同じような流儀で「キリスト教」という宗教をやるということです。こういう人たちも自分のことをクリスチャンだと思うでしょうし、世間もクリスチャンと呼んでくれるでしょう。でも、神さまの側からしたらどうでしょうか。人間的に見たら確かに立派かもしれませんが、実際には、神さまとの交わりもない、神さまの愛を守り行いもしない、そういう人をクリスチャンと呼んでいいのか、ということにならないでしょうか。 本日学びますみことばに登場しますサルディス教会も、そのような、名ばかりクリスチャンという問題を抱えていました。私たちが、名ばかりクリスチャンにならないようにするためにはどうすればよいか、サルディス教会を反面教師として、以下、ともに学んでまいりたいと思います。 サルディスは、7つの教会の中で地理的に中央にあり、交通の要衝でした。エペソからは東に80キロメートルの地点に位置する交通の要衝で、エペソの女神アルテミスのような、死者を生かす力があると崇拝されていたキベレの神像がありました。 キベレに死者を生かす力があったと信じられていたことを考えると、サルディスにおいては、死者の復活を説くキリスト教会に対して、一般人からも一定の評価が与えられていた可能性が考えられます。実際、サルディス教会は生きている教会という、人からの評価があった模様です。 生きている教会、という代名詞。私たちもそう言われたいでしょうか。でも、教会が生きているって、どういうことでしょうか。生きているというからには、いかにも荘厳な礼拝がささげられていたのでしょうか。教会員たちが活発に奉仕していたのでしょうか。立派な建物を有していたのでしょうか。 しかし、人が何と考えようと、神さまの御目から見れば、生きているとは名ばかりで、実際は死んでいました。生きているとは名ばかりで実際は死んでいる。それは、ヤコブの手紙にもあるとおりの、ある種のクリスチャンの生きようであり、彼らは、自分には信仰があると自負していても、実際にはそれに見合うだけの行いがないという生き方をして、ヤコブに責められていました。 神さまに認められる行いは何でしょうか。それは、神の国をこの地に立てよという主イエスさまのご計画を成し遂げることです。それは、みことばを機械的に守り行うという行いではなく、イエスさまを心から信じているゆえに、そのあふれるばかりの心で自発的に神を愛し、人を愛そうという、具体的に身を結ぶ行いです。そのような行いの実を結ぶ信仰生活をしないならば、クリスチャンはその信仰生活は形ばかりの宗教生活になり、実際は世を愛するようになり、道徳的に堕落するようになります。 サルディス教会のその行いを主がご覧になり、「生きているとは名ばかりで、実は死んでいる」と評価なさったにあたって、主は、サルディス教会に対する外部からの迫害ですとか、ユダヤ人による挑戦、教会内部の葛藤といったことを語っておられません。それは、それだけ、サルディス教会が世に妥協し、同化するようになっていたことが考えられます。 このような教会に対し、主はおっしゃいます。「目を覚まし、死にかけている残りの者たちを力づけなさい」。死んでいる、というのが主の評価ですが、それでも、信仰の炎がわずかに灯っていて、まだ死んでいない、そんな信仰の友を力づけなさい、と、命令されています。 このように語られると、ああ、死にかかっているのはほかの人で、自分はまだ大丈夫だ、などと思ったりしないでしょうか? しかし、英語や韓国語の聖書ですとか、リビングバイブルや柳生(やぎゅう)訳のような翻訳を読むと、これは、「あなたの」死にかかっている信仰の力を振りしぼれ、となります。責任はほかの人にあるのではありません。ほかならぬ、私たちひとりひとりにあるのです。 力を振りしぼって何をするのでしょうか? 主はおっしゃいます。「わたしは、あなたの行いが神の御前に完了したとは見ていない。」そうです、することは、行いを「完了させる」ことです。 でも、私たちはどうやって行いを「完了する」のでしょうか? 果たして行いで神さまに認められることなどできるのでしょうか? そこで私たちは、完了する、ということばを、掘り下げて考えましょう。私たちは「完了する」というと、何か連想しないでしょうか? そう、イエスさまが十字架のうえでおっしゃったことば、これが「完了した」でした。 主がサルディス教会を評価されるにあたっておっしゃった、「行いが完了した」は「プレロオー」という原語ですが、これはイエスさまが十字架でおっしゃった「完了した」というおことば「テテレスタイ」の基本形「テレオー」と、ほぼ意味が同じです。聖書によって「完了した」というイエスさまのおことばを「成し遂げられた」という別の表現で訳し分けるようなものです。つまり、サルディス教会に求められていた行いの完了は、イエスさまの十字架による行いの完了ということを抜きにしては語れないのです。 形だけみことばを守り行っていればいいという律法主義、どうせ許されているから何をやってもいいという無律法、どちらも間違いです。イエスさまは人に守れなかった、つまり完成できなかった律法を、十字架におかかりになることによって完成されました。 人は、イエスさまが完成してくださった律法を、守り行って救いを得るための手段ではなく、イエスさまが完成してくださったゆえに積極的に守り行うように変えられたのです。行いの完了は一生ものです。イエスさまを信じ受け入れることがまずは大前提となりますが、そのように信じてからは、イエスさまとともに歩む生活を欠かしてはなりません。私たちは行いを完了できません。主が完了してくださった、この信仰に歩み、その主のご栄光を積極的に現わそうと、愛の行いを主の御目から見た完了、完成に向けて日々こつこつと積み上げていくのです。 その歩みをしていくために必要なのはどんなことでしょうか? 3節をご覧ください。みことばを思い起こし、守り行い、悔い改めることです。まことの悔い改めも回復も、みことばをお聴きして、そのみことばに従順にお従いすることに始まります。その歩みをするために、私たちは日々みことばをお読みするのですし、お祈りをするのです。 しかし、ほとんどの場合、みことばをお聴きすることは個人的なことです。つまり、人の目に見えないところで自分から行うべきことです。教会によっては、聖徒たちが日々ともに主の御前に出るための取り組みとして、毎日の早天祈祷会を持っているところもあります。私はかつて、そういう教会で長らく副教職者として働いたものでしたが、一日でも早天祈祷会を休むと、主任牧師から烈火のごとく叱られたものでした。 事程左様に、主の御前につねに出てみことばを聴き、お祈りすることは大切なことなのですが、それならと、人の目に見えている早天祈祷に出てさえいればあとは大丈夫、というものではありません。大事なのは、人の見ていないところでも、きちんと主とお交わりを持つことです。私が教会のみなさまのために祈っていることは、みなさまが教会に集うときはもちろんのこと、教会に集っていないときにも、欠かさずに主とのお交わりを持つことです。 私たちがその敬虔な歩みをする上での最大のモチベーション、それは、主は近い、ということです。いつ主が来られるかわからない、それは、聖書が一貫して語っているメッセージです。 私たちは人に見えるところは敬虔でも、実際は肉にしたがう生活をしているならば、そこに再臨のイエスさまが来られたとき、果たして恥ずかしくなく御前に立てる自信、というより確信があるでしょうか? 大丈夫と言い切れますでしょうか? だからこそ私たちは再臨のイエスさまを意識して、たえず目を覚まし、悔い改めている必要があるのです。 ただ、私たちは夜になると必ず眠らなければならないように、私たちはその肉の弱さゆえに、戸口で待ち伏せする罪に対処できなくなることがあるものです。魔が差した、ということばがありますが、悪魔はそのように、時に罪を犯す私たちを罪に定め、おまえにはもはや神の赦しなどない、などというような攻撃を加えます。 そういう、今なお肉が生きていて、誘惑に惹かれる私たちであることを思うならば、目を覚ましつづけることに自信が持てなくなりもするでしょう。しかし、そのような私たちは、4節以下の神さまの御約束に目を留める必要があります。神さまが「その衣を汚(けが)していない」と評価してくださる、その評価をお受け取りできるのは、いったいどのような人でしょうか。 ヨハネの黙示録19章8節を見てみますと、聖徒の正しい行いは、花嫁なる教会が花婿なるキリストに嫁ぐにあたって身に着ける亜麻布のきよいウェディング・ドレスである、とあります。正しい行いとは機械的に正しくみことばを守り行うことではなく、イエスさまとの生きた交わりの中から生まれる自発的な従順、愛の具体的な実を結ぶことです。 きよい衣とは、純潔な花嫁としてキリストに嫁ぐ者にふさわしい、純潔な信仰を意味します。このイメージは、勝利を得る者に着ることが許される、白い衣のイメージとよく合致しています。実に、純潔な信仰とは勝利なのです。先週礼拝で歌いましたとおり、信仰は勝利なのです。 あとでおうちにお帰りになったら、旧約聖書のゼカリヤ書3章のみことばをお読みいただきたいのですが、このみことばをお読みすると、時の大祭司ヨシュアが神の法廷に引き出され、サタンに告訴されている場面が出てきます。神の民を代表して神の前に出るべき大祭司がサタンに告訴されたとは、ただごとではありません。 このときヨシュアは神の法廷において、汚れた服を着て神の御前に立ち、いかにも聖い神さまのしもべにふさわしくない姿でいました。しかし神さまは、ヨシュアを受け入れ、御使いはヨシュアの汚れた服を脱がせ、主の御前に立つにふさわしい礼服を着せました。 イエスさまが信仰により勝利を得る者に白い衣を着せ、その名を父の御前と御使いたちの前で言い表すとは、そういうことです。神の法廷において無罪を宣告し、それでも時に罪を犯してサタンに告訴されるような、その罪を十字架の血潮によって洗いきよめてくださり、かえって罪を告訴するサタンをとがめ、さばかれるのです。身に着けているものはきたない服ではありません。天国、新しいエルサレムに入る礼服である、白い衣です。 この者の名を、神さまはいのちの書から消すことは決してなさらないとあります。これは、いのちの書から消される人もいることは有り得る、という意味ではありません。決して消しはしない。つまり、必ずあなたを天の御国に入れる、と、強く約束してくださっているのです。 私たちは、自分はもしかしたら天国に行けないかもしれない、神さまはもしかしたら、自分の罪を赦してくださらないかもしれない、などとは、絶対に考えてはなりません。サタンは大胆不敵にも、大祭司ヨシュアを罪に定めて神さまに告訴しましたが、神さまにとがめられたのはヨシュアではなく、むしろとがめたサタンでした。 ヨシュアを罪に定めたサタンは私たちのことも告訴しますが、私たちもヨシュアと同じように、勝利する者にふさわしくきよい衣を着せていただけます。私たちも時に罪を犯します。あたかもそれは、着ている服が汚れるようなものです。 しかし、私たちには悔い改めの機会が残されています。その機会があるうちに御前に出て悔い改めるならば、神さまは私たちの罪をことごとく赦してくださいます。悔い改めは恥ずかしいことでも、みっともないことでもありません。私たちのことを天国に入れてくださっている神さまとの絆を確かめる、またとない恵みの時間です。 サルディス教会は宗教的にはすぐれた評価をもらっていたようでも、このような白い衣にふさわしい信仰の人がとても不足していました。私たちはどうでしょうか? サルディス教会のような、生きているとは名ばかりで実は死んでいる、という評価をいただかないようになりたいものです。 使徒パウロは第二コリント6章9節で、サルディス教会に対するこの神さまの評価と正反対の告白をして、「死にかけているようでも、見よ、生きており」と、キリストが内に生きる者の充実した人生を喜んでいます。パウロの告白は私たちの告白でしょうか? パウロはキリストのあとを追って十字架を背負う生き方をしましたが、それが真実に生きる道でした。 私たちは世と妥協して生きる道を選ぶならば、死にます。しかし、キリストのあとにしたがって日々自分を十字架につけるならば、生きます。私たちは生きたいでしょうか、死にたいでしょうか? 言うまでもないことです。しかし、私たちが真に生きるためには、キリストのゆえに自分を差し出し、神と人に仕える愛の実践が必要になります。 愛の実践、それが、神さまの御目から見て、行いが完了することです。私たちはそのようにして、神さまの律法、愛の律法を完成させてくださったキリストが内に生きる生き方をみことばへの従順によって実践してまいりたいものです。そして、その生き方がともに実践できたならば、兄弟姉妹でともにキリストの御名をほめたたえたいものです。 その生き方を日々していくならば、私たちはキリストがいつ来られても、恥ずかしくなく御前に立つことができます。私たちはイエスさまを待ち望んでいますでしょうか? 再臨を待望するなら、ますます、愛の行い、神の栄光の行いをこつこつと、ともに積み重ね、神の栄光を日々現わしましょう。イエスさまの再臨に向けて用いられる私たちとなりますように、用いられることを日々目指し、みことばの実践に日々取り組む私たちとなりますように、主の御名によって祝福してお祈りいたします。