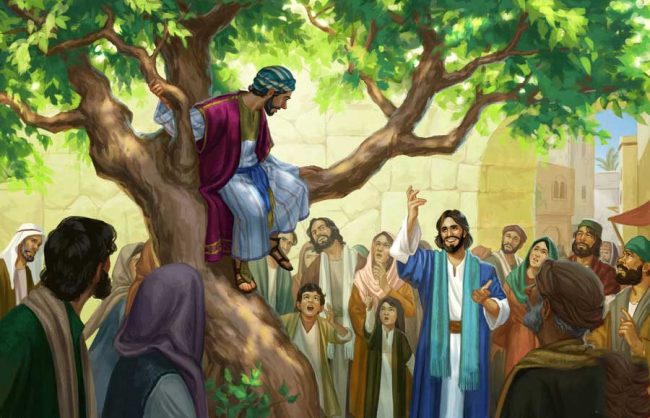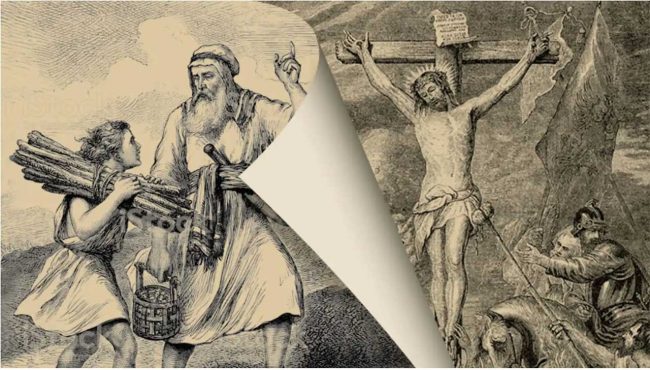「『その日』が近づく私たち」
聖書箇所;ヘブル人への手紙10章25節/メッセージ題目;「『その日』が近づく私たち」 昨年来の新型コロナウイルス流行は、戦後最大の危機を日本のキリスト教会にもたらしたと言えましょう。なにしろ、集まって礼拝をささげなくなっただけではありません。礼拝のために集まらないことが当たり前になり、さらには、集まらないことが、これほど正当化されたことがあったでしょうか。 新しい生活様式、などとよく言われましたが、新しい生活様式というものは、私たちキリスト教会にも否応なく押し寄せてきました。ただ、教会の場合、そのそれぞれの歴史、置かれた地域の特性によって、判断はさまざまであり、新しい生活様式なるものも教会によってちがいます。東京のような都会の教会は、集まらずにオンラインの礼拝中継に切り替える判断をした教会も少なからず存在したようです。 私たちの場合は感謝なことに、まだ大々的な感染拡大に至らず、1回も欠かさずに礼拝をささげつづけることができています。これは私たちが偉いのでもなんでもなく、恵みです。神さまにご栄光をお帰ししましょう。ハレルヤです。 ともに集まるかどうかという判断を下す場合もそうですが、私たちは何を基準に判断すべきでしょうか。やはりみことばです。もちろん、みことばどおりに行うことができなくて、苦しいところを通らされることも、教会としては充分にあることです。それでも、いざというときの判断の基準があるのとないのとでは、大きな違いがあります。 新聞やテレビの報道もたしかに大事でしょう。しかし私たちにとってそれらの報道は、絶対視するべきものでしょうか? 聖書とニュースと、どちらが大事でしょうか? 世相はいかようにも変わります。それらの揺れ動く報道を絶対視するならば、私たちも揺れ動くのであり、そうなったら、教会は果たして何のために存在するのか、教会を教会ならしめる聖書のみことばは何のために存在するのか、ということになりはしないでしょうか。 ただし私は、聖書とニュースは対立するものであると言いたいのではありません。言うまでもなく私たちの生きている現実は、ニュースという形で反映されていて、それを無視することはできません。要は、聖書のみことばから悟った真理を、いかにして、ニュースという形で映し出される現実の世界に反映させ、適用するか、ということです。 その原則から、今日のみことばをあらためてお読みしたいと思います。 まず、「ある人たちの習慣は、一緒に集まることをやめることであった」ということがわかります。 どうもこの時代のヘブル人クリスチャンの中には、一緒に集まって礼拝や交わりを持つことをやめて、単独で信仰生活を送ろうとしていた人が存在し、そういう存在が教会に少なからぬ影響を与えていた、ということが読み取れます。 一緒に集まることをやめる。理由はいろいろでしょう。この時代のクリスチャンは苛酷な迫害に晒されていたので、教会に集まるのは危険だと考えた、ですとか、あるいはもっと単純な理由、教会の中の人間関係につまずいて、もう教会には行きたくなくなった、ですとか。 そういう人たちの存在は、一緒に集まることをためらわせる大きな理由となったと思います。集まらない人はそれなりに正当な理由を持っている。右へならえ。いっそのこと、もうみんなで一緒に集まるのをやめてしまおう。 しかし、このみことばに示された原則は、一緒に集まることをやめてはならない、ということです。 一緒に集まることをやめてはならない。昨年の新型コロナウイルス流行で多くの教会は集会を中止しましたが、恐らくそれらの諸教会の聖徒たちの中にはこのみことばがあり、相当な苦渋の決断を強いられたことと思います。そんな諸教会のことを、うちのような集まりが持てた教会は決してさばくべきではありません。私たちはむしろ、このみことばを守り行う恵みを与えてくださった神さまに、心からの感謝と賛美をおささげするべきです。 しかし、もし集まることが許されているならば、私たちは決して、一緒に集まることをやめてはならないのです。それが、聖書のみことばが私たち聖徒たちに命じていることです。 では、なぜ私たち聖徒は、一緒に集まることをやめてはならないのでしょうか。それは「励まし合う」ためです。 信仰生活というものは、ひとりでするものではありません。ひとりで信仰生活ができるならば、教会というものはそもそもいりません。教会は共同体です。それは、神さまというお方が、おひとりであられるのと同時に、御父、御子、御霊の三位一体の共同体でいらっしゃるようにです。 お互いがもっと神さまにつながっていられるように。お互いがもっと神さまのみことばを守り行い、神さまのご栄光を顕せるように。そのために、お互いを覚えて祈る。この共同体の営みがあってこそ、私たちはともに信仰が増し加わっていくのです。教会という場で聖徒たちが励まし合うことで、私たちはそれぞれの信仰が成長するのです。 したがって、励まし合うためにともに集まるのでないならば、その集まりには意味がありません。励まし合いが集まりの目的となっていないならば、どうだ、よその教会とちがってうちは集まれたぞ! などという、的はずれな誇り、パリサイ人のような誇りにつながってしまいかねません。 そのように、聖徒たちが励まし合う理由……それは、その日が近づいている、ということです。その日とは何でしょうか? イエスさまが再び来られる日です。 このみことばからわかることは、イエスさまの再臨は、教会が始まったばかりのこの時代から、すでに切に待望されていたものであった、ということです。すぐにでもイエスさまは来られますよ、私たちキリストの花嫁なる教会はいっしょに、灯を掲げて、花婿なるキリストを待ち望みましょう……。 花婿なるキリストを待ち望むことは、ひとりですべきことではありません。いっしょになって、ともにみことばをお読みして、お祈りして、みことばを守り行いながら、教会全体で待ち望むものです。この水戸第一聖書バプテスト教会が待ち望みます。日本のすべての教会が待ち望みます。世界のすべての教会が待ち望みます。 この1年で、世界の教会はオンライン礼拝、リモート礼拝が花盛りとなりました。それは時代の趨勢、時代の要請と言えることでしょう。しかし、ここで憂慮されることがあります。それは、リモートで礼拝することによって、キリストのからだなる教会のひと枝とされている意識が希薄になってしまう信徒が多く現れてしまうのではないか、ということです。 ともに礼拝堂に集う場合と比較してみましょう。礼拝堂に集うならば、ちゃんと早起きして朝ご飯を食べ、女性の方ならばしっかりお化粧するでしょう。そして、威儀を正し、車に乗って数十分の時間をかけて礼拝堂に行きます。もうその時から祈り心をもって整えられているわけです。そして礼拝堂に到着し、礼拝室の中に入ったらお祈りします。これだけでも相当な心構えです。 しかし、リモート礼拝の場合、そこまでの準備をなさいますでしょうか。それができているならば素晴らしいことですが、何しろ家でパソコンに電源を入れ、インターネットに接続したら、すぐ礼拝です。ともに集うために祈り心を持って準備するという意識を持つか持たないかは、事程左様(ことほどさよう)に違ってしまうわけです。 だから、もしどうしてもリモートでなければ礼拝できない、という方は、それだけ充分な祈り心をもって礼拝に備えていただきたい、と、切に願います。特にその祈りを、神さまに向けてくださるのと同時に、所属していらっしゃる教会という共同体の兄弟姉妹を覚えての祈りとしていただきたいと思います。 要は、イエスさまの再臨にともに備えて、励まし合うために、共同体に召されたどうしを大切にすることです。いまこうして集っていられることは、集うこともままならないでいる教会から見ればとても贅沢なことです。この恵みをむだにしないでいただきたいのです。 今日、ここに集う兄弟姉妹のことを、再臨をともに備えるために励まし合う、大事な兄弟姉妹と考えていただきたいのです。そして……ここにともに集っていなくても……クリスチャンであるならば、同じイエスさまの十字架の血潮によって贖われ、神さまの子ども、天国の民にしていただいたどうし、ともに再臨を待ち望みつつ励まし合う、大事な存在です。 今年、うちの教会は、世の終わりがいかに訪れるかを語るみことば、ヨハネの黙示録から学びます。それは、単に聖書知識を増し加えるためではありません。みことばにともに耳を傾けることで、水戸第一聖書バプテスト教会というこの群れに主が持っておられるみこころをともに知り、励まし合うためです。 最後に、私たちはいかにして励まし合うものとなるべきか……やはりそれはみことばによってです。一箇所みことばを開(ひら)きたいと思います。ペテロの手紙第二、3章3節から9節です。 ある人は、私たちが終末ということを本気で信じていることを嘲るでしょう。もしかしたら私たちクリスチャンまで、そのような世の風潮に毒され、終末を語る主のみことばをまともに取り合わなくなってしまわないとも限りません。しかし、神さまは終末ということをはっきり語っています。 しかし、この終末のさばきは水のさばきではなく、火のさばきです。水のさばきも火のさばきも、どちらも恐ろしいですが、この最後の火のさばきは、不敬虔な者たち、すなわち、まことの神さまを神としない生き方を悔い改めない者たちに対して行われるものです。 私たちはこのさばきを免れ、救っていただく存在であることを覚え、感謝しましょう。でも、それだけではなく、さばき主なる主のさばきを覚え、ひとりでも多くの人がこの終わりの日のさばきから免れるように祈り、救い主イエスさまを今年も伝えてまいりたいものです。 そして主がこの世界に対し、忍耐しておられることも考えましょう。私たちの生きるこの世界は、イエスさまが天に昇られてからずっと、罪人の歴史、罪の歴史と言えるものでした。2000年間再臨がなかったからこれからもない、ではありません。2000年間、よくぞ忍耐してくださり、私のことを生かしてくださいました、感謝いたします、私たち教会はあなたさまを待ち望みます、こうでなければならないはずです。 私たちは去る2020年、再臨を待ち望んでいましたでしょうか? 再臨はないかもしれない、という、不信仰になってはいなかったでしょうか? あるいは、再臨のことなど考えもしないで、自分勝手に振る舞うことも多くはなかったでしょうか? はたまた、再臨なんてどうでもいい、と、無関心になってはいなかったでしょうか? もしそうだったならば悔い改め、今年こそ、必ず来られるとみことばにおいて約束しておられるイエスさまのその約束を心から信じ、イエスさまにのみ希望をおいて、ともに歩んでまいりましょう。 では、お互いのことを覚えて祈りましょう。