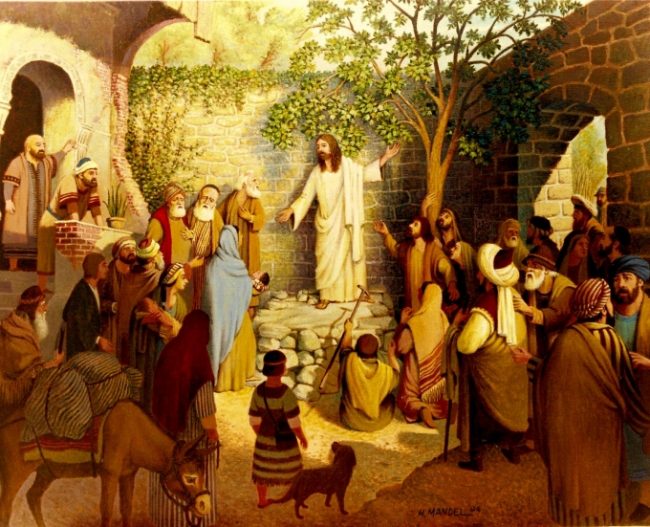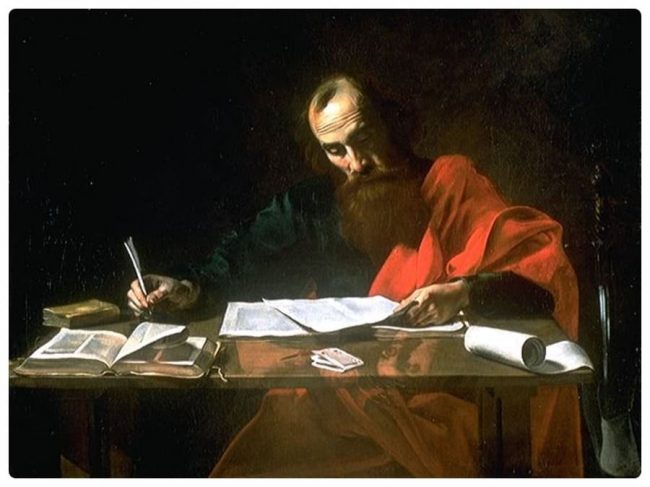「主イエスの母、そして主イエスの家族」
聖書箇所;マタイの福音書12:46~50/メッセージ題目;「主イエスの母、そして主イエスの家族」 私は韓国に留学した1995年、「ソウル日本人教会」という教会に通っていました。その教会は、韓国訪問の折に教会に訪れるさまざまな日本の牧師先生が、日本のキリスト教会で起きていることをリアルタイムに伝えてくださる場となっていました。その先生方のメッセージの中で、忘れられないものがありました。その年は阪神淡路大震災が起こった年でしたが、当時、日本基督教団新潟教会の牧師でいらっしゃった、春名康範先生という方がいらしたとき、こんなことを語っていらっしゃいました。 震災からの復興活動での炊き出しに参加され、そのときの様子に、ある韓国語を思い出したというのです。それは「シック」ということばでした。「シッ」は「食べる」と書き、「ク」は「口」と書きます。「食べる口」というわけですが、これは「家族」という意味です。春名先生は、ボランティアの炊き出しに群がり、一緒にご飯を食べる被災者の、ああ、ありがたいなあ、というその姿に、シック、という韓国語を重ね合わせた、とおっしゃったのです。まさに、同じ大きな災いを通して、避難所で家族のような立場になったどうしが、同じ食べ物を食べて、シック、つまり、家族……なるほど……私は唸りました。 当時私は、韓国の地方からソウルに上京していた7人の大学生たちとひとつ屋根の下で共同生活をしていました。朝には交替でごはんをつくります。食べるときは鍋を真ん中において、お椀にもつがずにスプーンで直接すくって飲みます。キムチもおかずも、取り皿なんてありません。そして朝ごはんがすんだらそれぞれキャンパスに散り、夜になると帰ってきます。寝る前には車座になって、一日のできごとの報告とお祈りの課題をそれぞれ話し、最後にみんなで手をつないで祈ります。まさに「家族」。 私はその、春名先生のエピソードに感動した日、家に帰り、同居していた学生リーダーにそのことを話すと、彼もとても感動してくれました。やがて私が留学生活を終えて日本に帰るとき、彼はみんなの前で、トシ兄弟が言っていた「シック」のエピソードにとても感動した、俺たちはいっしょに食事を囲む家族じゃないか、という意味のことを、わざわざ言ってくれたものでした。 今日は礼拝において「主の晩さん」を分かち合います。先週金曜日、私は保守バプテスト同盟の教職者の勉強会である「同盟アーカイブズ」というものにオンラインで出席しました。そのとき教えられたことですが、ほんらい「主の晩さん」というものは儀式ではなく、主にある交わりの一環として行われた食事の一部であった、ということです。それが、時代が下るにつれて宗教的な意味づけがされ、いつの間にか、とても畏れ多いものとなってしまった、ということです。 本日、ともにいただく「主の晩さん」は、どうか、イエスさまが手ずから裂かれたパン、イエスさまが杯を回されたぶどう酒をともにいただく、家族としてともにいただく、そういう気持ちであずかってまいりたいと思います。そんな「主の晩さん」を控えた私たちは、同じ主の晩さんのパンと杯を食して口にする「シック」、家族であるわけですが、それがどんな家族なのかを、イエスさまが端的にお示しになったみことばから、今日はともに学び、ともに家族とされている喜びを分かち合いたいと思います。 今日の箇所は、イエスさまの母であるマリアと、イエスさまの弟たちが、イエスさまに会いにやってくる場面から始まっています。マリアのことは申し上げるまでもありません、あのマリアです。イエスさまの弟たちというのは、マリアとヨセフの間に生まれた人たちで、「主の兄弟」という別名で呼ばれることもあります。名前はマタイの福音書13章の終わりの部分で明らかになってもいますが、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダで、このうちヤコブとユダは、新約聖書の「ヤコブの手紙」「ユダの手紙」を書いた人物で、つまりは初代教会の指導者になった人です。ついでに申し上げますと、イエスさまにはこの4人の弟のほかに、少なくとも2人の妹がいたことが、やはりマタイの福音書の13章からわかります。 また、これは類推ですが、イエスさまの公生涯の記述に、ヨセフのことが出てこないのは、イエスさまの公生涯の時期にはヨセフがすでに亡くなっていたからだというのが定説です。ヨセフがなぜ亡くなったかは、聖書はまったく沈黙しています。しかし、ヨセフは少なくとも、あまり健康が保てる仕事についていなかったのはたしかです。石で家を建てる時代のパレスチナで大工となったら、石を切ったり削ったりする作業で大量の粉塵が出て、マスクもない時代です、その粉塵を吸い込んで、健康をとても害したことでしょう。イエスさまがお生まれになったヨセフの家庭は、そのような厳しい労働者の家庭だったということを、私たちは覚えておきたいと思います。 イエスさまはもともと、そのような家庭の長男として、稼ぎ頭だったわけでした。しかし今やイエスさまは、神の国を宣べ伝えるお方でした。そのようなお方でしたが、ユダヤ人ならだれもかれもがイエスさまのことを受け入れていたわけではありませんでした。同じ12章をご覧ください。イエスさまはパリサイ人から、悪霊のかしら扱いされています。もちろんイエスさまは、それに対してごもっともな反論をしていらっしゃるわけですが、このように、当時絶対的な立場にあった宗教指導者たちに睨まれていたことは、マリアや弟たちを動揺させるに充分だったのではないでしょうか。そんな彼らがイエスさまに話しにやってきたわけです。お願いだから、悪いことは言わないから、こんな働きはやめて……。そんな彼らの心の声が聞こえてくるようです。 親兄弟が会いに来たならば、会うべきだと思いますでしょうか。しかし、イエスさまは取り継いだ人に対し、みなの聞いている前でおっしゃいました。48節から50節です。……イエスさまは、ご自分に弟子としてついてきていた人たちのことを、わたしの母、わたしの兄弟たち、とおっしゃいました。それはなぜであるか、50節に語られているとおりです。彼ら弟子たちは、天におられるイエスさまの御父のみこころを行なっているからだとおっしゃいました。 ここから、2つのことが分かります。ひとつは、イエスさまのお働き、神の国を宣べ伝えるお働きをとどめようとすることは、いかにイエスさまの肉親であろうとも、とどめることはできないし、また、とどめるべきではない、ということです。もうひとつは、天の父なる神のみこころを行うならばその人がほんとうの弟子である、その、神のみこころを行うとは、イエスさまに弟子としてついて行くことである、ということです。 イエスさまは、「だれでも天におられるわたしの父のみこころを行うなら」とおっしゃいました。ここでマリアたちも、群衆も、弟子たちも、そして私たちも、イエスさまの父とはどなたなのかを考える必要があります。 マタイの福音書の13章に入ってみると、イエスさまの故郷ナザレの人たちは、イエスさまはヨセフのせがれ以上の見方をしなかったわけです。マリアたちも、イエスさまのことをそのようにしか見ることができなかったからこそ、このようにイエスさまのお働きに関係なく、お働きの最中でも呼びつけるようなことをしたわけです。しかし、イエスさまの父なるお方はヨセフではなく、天のお父さまであることを知るならば、人はイエスさまの弟子になるならば、すなわち天のお父さまのみこころにお従いすることになります。イエスさまは、肉親の関係でご自身のご家族を決められるお方ではありません。天の父なる神さまを父としてイエスさまに従う人ならば、だれでも家族としてくださるのです。 天の父のみこころを行うなら、とは、それは、天の父をイエスさまのゆえに信じる、ということです。イエスさまを通してでなければ、だれも天の父のもとに行くことはありません。しかし、イエスさまを通すならば、人はだれでも、創造主なる神さまをお父さまとお呼びする者としていただけます。これが、信仰を持つ第一歩であり、それはまた同時に、イエスさまの弟子となる第一歩でもあります。しかし、イエスさまは私たちにとって遠いお方ではありません。私たちのことを家族として受け入れてくださいます。 さて、家族、というとき、「兄弟姉妹」なら、まあ私たちはわかるのではないでしょうか?例のベートーヴェンの「第九」のメロディの聖歌、25番の4番の歌詞は、「御神はわれらの父親なれば/御子なるイエスをば兄上と呼ばん」とあります。私たちはあまりイエスさまのことを「お兄さま」と呼ぶことはないように思いますが、まあ、論理的にそうなのはお分かりだと思います。私たちは同じ御父によって、イエスさまの兄弟姉妹にしていただいている存在です。 しかし「イエスさまの母」となりますと、これはどうでしょうか? イエスさまのこのみことばはかなり難解です。私たちは百歩譲って、イエスさまの弟や妹に加えていただけるとは思うでしょうが、「母」となると、あまりに畏れ多い、と思えませんでしょうか? しかしこのイエスさまのおことばは、ほかならぬマリアがどういう理由で訪ねてきたか、ということを考えると、謎は解けます。イエスさまは「だれでも天におられるわたしの父のみこころを行うなら、その人こそわたしの……母なのです」とおっしゃっています。ということは、このときマリアは、天の父のみこころを少なくとも行なっていなかった、ということになるわけです。 マリアは何をしたのでしょうか? マリアは主の兄弟たちとともに、群衆のいる家の外にいました。要するに、イエスさまについて行っていたわけではありませんし、イエスさまが説いておられるメッセージそのものに関心があったわけではありませんでした。 ということは、マリアも含め主の肉の家族は、イエスさまの語っておられる神の国に無関心な態度を示していた、ということになります。それだけでしょうか? イエスさまがいっしょうけんめい、神の国の福音を語っていらっしゃるというのに、そこに主の兄弟たちとやってきて、イエスさまを呼びつけたということは、結果的にその行動は、イエスさまのそのお働きを中断させてしまうことになるわけです。 それはどういうことでしょうか。神の国の福音が、それだけ聞く人に伝わらないということになります。人が救われて神の国に入る可能性は、それだけ損なわれることになります。それはイエスさまの、神の子キリストとしての働きを邪魔することであり、つまりは天のお父さまのみこころをきわめて損っているということです。 しかし、さすがはイエスさまなのは、そのような無理解なマリアたちの行動さえも、神の国の福音を人々に解き明かす機会へとお用いになったことでしたが、ともかく、マリアは、ルカの福音書1章で告白したように、神の子イエスさまをこの世に送り出した主のはしためとしての立場を堅持している必要がありました。 それこそが、神の子キリストの母であるということです。キリストを生んだ人、というよりは、主のはしため、主に用いられることに至上の喜びを覚える謙遜な器、だからこそ、御父はイエスさまをこの世に送り出す人としてマリアをお選びになったのであり、私こそはイエスの母親でござい、というような振る舞う人は、いちばんイエスさまの母親と呼ばれるのにふさわしくない人です。 しかしこの、イエスさまに「わたしの母」と呼んでいただいた、その場でイエスさまのメッセージをお聴きしていた弟子たち、とくに女性の人たちがどんなに面映(おもはゆ)い思いをしたことか、想像するにあまりありますが、イエスさまの母、という面映ゆい呼び名は、イエスさまにそう呼んでいただいた人以外にふさわしい人などいないと考えるべきです。言うまでもないことだと思いますが、間違っても自分たちの間で、あら、あなたは神のみこころを行なっているわね、あなたはイエスさまのお母さまね、というようなレベルの話ではありません。あまりに畏れ多くて、そんなことはとても口にできないのがクリスチャンとしてのまともな神経でしょう。 マリアの話に戻りますが、マリアもまたひとりの人として、父なる神さまのお取り扱いのもとに身を低くする必要がありました。 イエスさまの献児式のためにエルサレムにヨセフとマリアが赴いたとき、シメオンがイエスさまについて、このような預言をしました。ルカの福音書2章、34節と35節です。……まさにさばき主なるイエスさまによって、マリアの心さえも、まるで剣が刺し貫くようにさばかれる、というわけです。マリアはこのとき、イエスさまのお働きを妨害したとは、自分は実は神のみこころを行なっていなかった、という現実を見せつけられました。マリアもまた、悔い改める必要があったのでした。 しかし、このようなマリアでしたが、聖書は、イエスさまの十字架のできごとにおいて、マリアがどうだったかを記しています。マリアは、イエスさまの十字架の前に立っていました。イエスさまの十字架をじっと見つめていたのです。イエスさまはそんなマリアに、ご自身の愛弟子ヨハネこそ、これからあなたと親子になる人です、とお語りになり、神の家族としての新しい家族の関係にマリアを導き入れられました。 マリアはもはや、私はイエスさまの母でござい、の人ではありませんでした。神の家族に生きることによって父のみこころを行うことで、マリアはようやくほんとうの意味で「イエスの母」となることができたのでした。 私たちは自分から「イエスの母」を目指すことなどできませんし、ましてや、名乗ることなどできません。しかし、「神のみこころを行う弟子となる」ことで、イエスさまの家族に加えていただくことはできます。イエスさまに肉親の家族が実際にあったわけですが、それ以上に強い関係として、私たちのことを家族にしていただけるのです。 私たちは今日、主の晩さんをもってパンとぶどう酒をともにいただきます。それは、イエスさまのみからだと血潮という主の食卓にともにあずかる、ひとつの家族であることを確かめる、おごそかにして麗しいひとときです。 私たちはイエスさまが、わたしの家族と呼んでくださった、特別な関係です。イエスさまと家族にしていただいている、これ以上素晴らしいことがあるでしょうか? 私たちは血を分けた家族との関係に、時に傷つき、いやな思いをします。しかしそれは、地上の家族が完全ではないからです。しかし、イエスさまと家族にしていただいている関係は、この世の何ものにも代えがたい関係で、私たちはこの、教会という共同体の中で、神の愛を体験し、兄弟愛をはぐくみます。 イエスさまは、私たちが家族としてますます愛に進むことを願っていらっしゃいます。そしてそれだけではなく、私たちに与えてくださったこの愛を、さらに多くの人に広げることを願っていらっしゃいます。私たちは今週、どのようにしてこの愛を味わいますでしょうか? そして、この愛をだれかに対して表現しますでしょうか? 私たちはだれかに愛をあらわしてこそ、イエスさまに愛されていることをほんとうに理解し、体験するようになります。