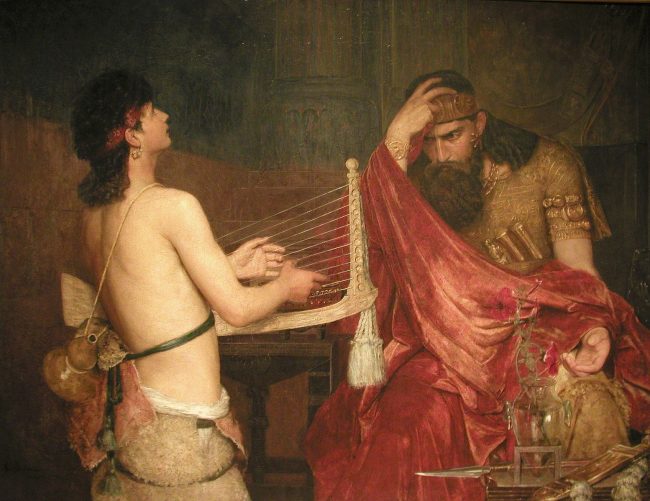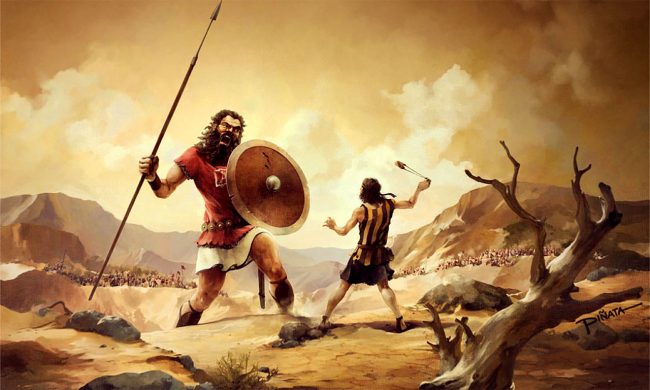礼拝は生活、生活は礼拝
聖書箇所;ローマ人への手紙12章1節/メッセージ題目;礼拝は生活、生活は礼拝 今年度、2022年度の標語は、「礼拝は生活、生活は礼拝」に決めさせていただきました。みなさま、今こうしておささげしている礼拝は、生活なんです。そして私たちの日々の生活は、礼拝なんです。この前提で私たちは、礼拝し、生活してまいりたいものです。 今お読みしましたみことばは「ですから」ということばで始まります。何が「ですから」なのでしょうか? そう、それは、ここまでの11章分の、ローマ人への手紙の内容を受け取っての、「ですから」ということです。 みなさま、ローマ人への手紙は毎日の通読とは別個にでも、何度でも繰り返しお読みいただきたいのですが、ローマ人の手紙が語っていることは、人間は全面的に堕落してしまっているということ、自分の力では一切、救われる道はないということ、しかし、私たち人間がまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神さまは私たち人間に愛を示してくださった、ということです。 私たちは行いによって救われるのではない、信仰によって救われた。そのように、救っていただいた者としてふさわしくあれ、ということで、「ですから」と語っているわけです。私たちはそれまで、罪と死と悪魔を主人としてそれらのおぞましい存在に奴隷として仕える存在でした。希望などありません。しかし私たちは今や、自由にしていただきました。今からはこのように自由を与えてくださったお方、神さま、イエスさまのしもべとして生きることが、私たちのすることです。 ということは、神さま、イエスさまが主人なわけですから、主人でいらっしゃる神さまが、私たちに何を求めていらっしゃるかを知ることが、私たちにとって何よりも大事になります。こうすれば神さまを喜ばせることができる! 私たちもいろいろ考えるでしょう。しかし私たちが、何かの行いをしたとしても、そのピントが外れていては、何にもなりません。 19世紀のアメリカの大衆伝道者、D・L・ムーディが、面白いたとえ話を語りました。ある男の子が、お父さんを喜ばせたいと思った。どうしたら喜んでもらえるかな? そうだ! お父さんは魚のマスが大好きだ! そこで男の子は、マスを釣りに行きました。……学校を休んで。……私たちクリスチャンもしばしば、こういう間違いを神さまに対して犯してしまう、というわけです。そこで私たちは、神さまが何を願っていらっしゃるかを、聖書から正確に知ることが必要になってきます。 このローマ12章1節によれば、そのみこころとは、「あなたがたのからだを、神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げる」ことです。旧約聖書を読んでみますと、祭司が神さまにささげものをいかにささげるべきか、という規定が繰り返し出てきます。しかし何よりも、そのささげ物は「傷がないもの」でなければならない、ということです。 しかし現実の私たちを見てみましょう。傷だらけではないでしょうか。きたないではないでしょうか。こんなものが果たして、神さまに受け入れられるのでしょうか? 答えは「イエス!」。ただし、条件があります。そのままではいけません。よく「そのままでいいんだよ」ということが語られますが、私たちにはそれでも条件があります。それは「イエスさまの血潮によって洗いきよめられる」ということです。 そのために私たちは、信仰を用いるのです。「私のすべてはイエスさまの十字架の血潮によって洗いきよめられた!」こう宣言するのです。そうなるともはや私たちは、傷のある者ではありません。きたない者ではありません。 しかし、そうなったら、私たちのすることはなんでしょうか? イエスさまの血潮によって洗いきよめられた者として振る舞うことです。もう、罪の性質を発動させないことです。「そのままでいい」といっても、捨てるべき罪の性質、悪意、むさぼり、姦淫、深酒、そういったものを捨てないままの「そのままでいい」ということではありません。 私たちがもし、主との交わりをしっかり持っているならば、そのような罪の性質から私たちは遠ざかることになります。もし、そのような生活の変化が現れないで、ただの人のように生きているならば、その人は神さまとの交わりを充分に持っているとは言えません。 私たちは日曜日ごとの礼拝をとおして、神さまの御前に出ます。このとき、私たちは聖霊の交わりをいただいて、みことばと祈りと賛美によって、神さまの御前にきよめをいただきます。また、毎日のディボーションと聖書通読をとおして、私たちはきよめをいただきます。それが大前提となりますが、しかし、それ「だけ」では私たちは「聖なる生きたささげ物」になりきることは極めて難しいです。私たちは、礼拝のたびに、また、ディボーションのたびに、みことばが何を語っているか、すなわち、自分に対して神さまはどのようなみこころを持っていらっしゃるかを知ることが必要になります。 つまり、みことばを聞くことだけで満足してはならない、ということです。単にみことばを聞くだけで満足して、それで生活が何も変わらないようでは、「宗教」をやっているにすぎません。私たちは、生活が変わっていく必要があります。 しかし、生活が主のみこころに従うように変わることは、私たちの力で何とかなることではありません。なぜならば、私たちは主のみこころにかなう歩みをすることなど、愚かなこと、面倒くさいことと思うような、肉の性質が意地悪く自分の中に存在するからです。 聖霊なる神さまに働いていただく必要があります。瞬間瞬間、聖霊さまのお導きに明け渡すのです。それゆえ私たちは、普段どんな働きをしているとしても、お祈りが欠かせませんし、聖霊さまのお導きに敏感になる必要があります。 そのようにして聖霊に導かれた生活をするとどのようになるか、と申しますと、神さまの栄光を顕す生き方が実践できるようになります。そのように、神さまのご栄光を顕す生き方こそ、礼拝の生き方、自分自身を神さまにおささげしつつ生きる生き方です。その生き方によって神さまに喜んでいただけるならば、これほど素晴らしいことがあるでしょうか? いや、神さまは私たちの存在そのものを喜んでおられるのだ、そのようにおっしゃいますでしょうか? それは確かにそのとおりです。しかしそれは、こういうことではないでしょうか? だれも、自分の子どもの存在を喜ばない親はいません。子どもはいてくれるだけで、親はうれしいものです。しかし、その子どもが親の心をしっかり受け取り、親に従って生きるのと、親に無関心で、親のことなどどうでもいいという態度で生きるのとでは、どちらがよりうれしいでしょうか? 神さまとの関係にも同じことが言えます。神さまは、神さまに背を向けていた私たち人間を愛して、ひとり子イエスさまを十字架につけてくださいました。私たちはこれほどの愛を受けているのですから、その神さまのみこころである、神さまを礼拝すること、日曜日の礼拝においても礼拝し、毎日時間を割いてでも礼拝し、そして、普段の生活のさまざまな取り組みをとおして、神さまのご栄光を顕すということをもって、神さまを礼拝する、そのような生き方をしてしかるべきではないでしょうか? この、礼拝の生活を、私たち水戸第一聖書バプテスト教会の兄弟姉妹で、ともにしてまいりたいのです。この生活は一人の取り組みでできるものではありません。その取り組みができるように、励まし合い、祈り合う共同体を築いてまいりたいと思います。 毎週日曜日の礼拝をともに充実させましょう。そして、毎日の礼拝の生活をともに充実させましょう。そのようにして、神さまに喜ばれる歩みをする私たちとなりますように、主の御名によってお祈りいたします。 お祈りしましょう。今年私たちは、「礼拝が生活、生活が礼拝」とますますなるために、ひとつ決心したいと思います。 毎日ディボーションします、と決心したならば、「毎日何時何分から何時何分まで」という目標をつくりましょう。毎日お祈りします、と決心したならば、「何時から何時まで」という目標をつくりましょう。また、週に1回は礼拝堂にお見えになり、お祈りされることを心からお勧めします。あるいは、礼拝にいらっしゃるのもコロナ下という状況で難しい、という方も、せめて、オンラインによる礼拝の同時中継に協力していただければと思います。パソコンを置くスペースは、きちんと片づけましょう。そこを祈りと礼拝の場として整えましょう。